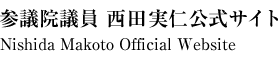財政金融委員会・4号 2007-03-15
【質疑事項】
「所信質疑」金融大臣、東証
1.「東京国際金融特区」について
2.東証の体制改革及び上場廃止制度について。
3.格付け機関の行動規範について
4.消費者金融大手の収益悪化見通しへの評価
5.中小企業向け動産担保融資について
6.ヘッジファンド規制について
「国税二法質疑」財務大臣
1.日本の財政の現状及び財政再建の方針について
2.国債残高膨張について
3.法人税率の引き下げについて
○委員長(家西悟君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告申し上げます。
昨日、大塚耕平君が委員を辞任され、その補欠として岡崎トミ子君が選任されました。
─────────────
○委員長(家西悟君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
財政及び金融等に関する調査並びに平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として財務省主税局長石井道遠君外九名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(家西悟君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
─────────────
○委員長(家西悟君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、参考人として株式会社東京証券取引所代表取締役社長西室泰三君及び日本銀行総裁福井俊彦君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(家西悟君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
─────────────
○委員長(家西悟君) 財政及び金融等に関する調査を議題とし、財政政策等の基本施策に関する件及び金融行政に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
○西田まこと君 公明党の西田でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。
また今日、東証の西室社長にも大変お忙しい中、また御足労いただきまして誠にありがとうございます。
今日、大臣所信に対する御質問ということで、この所信の中にもございましたとおり、我が国の市場を金融・資本市場の国際金融センターとしての魅力を更に向上させていくことが重要であると、こういう御指摘があって、私もそのとおりだろうというふうに思うわけであります。
山本大臣におかれましては、今年一月八日にロンドンに行かれまして、その際、イギリス大蔵省の経済担当大臣とかイングランド銀行の総裁とか、あるいはロンドン市長とも会談をなさって、シティーに匹敵する東京国際金融特区構想を打ち出したと報道されております。毎日新聞なんかのインタビュー記事も拝見をさせていただきましたけれども、その特区とするかどうかは別としても、魅力ある、国際的に魅力のある市場をつくっていこうという御構想を打ち出されたんだというふうに思っております。
確かに、東京のマーケットはニューヨークに次ぎまして株式時価総額を誇っておりますが、外国企業の上場数とか見ると、これはもうニューヨークが四百五十社とかシティーが三百三十社でしょうか、東京は本当にその十分の一程度、こういう現状にございます。
そういう意味では、この魅力ある国際的な市場をつくっていくことによって、海外企業の上場を増やして、また国内金融資産の優良投資対象を増やしながら、外国金融機関も誘致して国際金融都市東京というものの盛況を図っていくと、こういう御趣旨じゃないかと思うんですが、今日は大臣の貴重な御意見として、大臣が御構想されている今の思いを、この東京マーケットを国際的な魅力あるマーケットにしていくという点で、まずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) 私の認識の背景にあります数字を少し申し上げたいと思います。
世界と日本の株式時価総額についてでございます。一九九〇年に世界の時価総額が八・九兆ドルございました。うち東京が二・九兆ドル、言わば三〇%のシェアを占めておりました。二〇〇六年、去年で見ますと、世界の時価総額が四十九・九兆ドルございます。うち東京が四・六兆ドル、一〇%を切ってしまいました。言わば、その意味において、時価総額だけの面から考えれば世界の中に占めるシェアが三分の一になったと、こういう現状がございます。そしてまた、証券市場における時価総額の伸びで考えてみますと、一九九〇年と二〇
〇六年を比較したとき、東京はこの十五年間に一・五八倍、上海が五十五・六九倍でございます。また、シンガポールは十一・二一倍、香港は二十・五七倍。つまり、アジア関係が急激に伸びております。そして、ニューヨークも五・七三倍という数字でございまして、ロンドンは四・四六倍、ともに、それぞれ世界の経済成長とともにストックマーケットにおけるそういう資金も環流されているという、そういう現状がここ十五、六年で見られるわけであります。
しかし、その地球的な繁栄の勢いに若干東京は取り残されているという認識が私にございまして、そこで何をどうすればいいのかということでございます。報道等で金融特区という言葉が出ているようでございますが、自分が常々申し上げているのは、ロンドンのように高度な金融機能を集積させることによって日本全体の発展につなげていきたいということでございまして、いわゆる特区とは異なる意味合いを持つものと考えております。少子高齢化が進み、人口減少時代の到来を迎える中、今後とも我が国が経済成長を続けていくためには、一人当たりの所得の向上を目指す必要がございます。こうした観点から、これまでのように製造業だけに頼るのではなくて、高付加価値を生み出す金融サービス業を中核的な産業として位置付けていくことが必要だろうというように考えております。
また、グローバルな市場間競争が激化する中で、我が国金融・資本市場の国際的な競争力を強化するためには、貯蓄から投資への流れをより一層確かなものとし、内外の投資家が安心して投資できるような魅力ある市場を構築することが重要であろうと考えております。こうした問題意識の下、先般、金融審議会に我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループを設置いたしまして、金融制度に関する議論にとどまらず、人材、専門サービス、インフラ等、多岐にわたる課題について幅広い観点から議論していただいているところでございます。
金融庁といたしましては、こうした議論も踏まえまして、我が国市場の国際競争力の強化に向けた方策について検討してまいりたいと考えるところでございます。
○西田まこと君 これは確認ですけれども、この東京の国際金融市場にしていこうということにつきましては、金融庁の今のお話の審議会と、あと総理がお作りになっているこのアジア・ゲートウェイ戦略会議、また経済諮問会議のスタディグループというんでしょうか、この三つのところで同じようなテーマでやっていると思いますが、これは今後のスケジュールというか、それを、三つそれぞれ研究して、いずれ一つにしていくんでしょうけど、どんな感じでお考えなんでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) まずは官邸のアジア・ゲートウェイは、アジアについての成長と日本の関連をやっておられまして、それから経済財政諮問会議の専門家委員会につきましては、言わば学識経験的な発想からそうしたアプローチをされておられます。で、金融庁の金融審議会は実務家、つまり国際取引やストックマーケット関係者を中心にして、さて、この実務家的発想からすると何が必要で何が不足しているかというようなことについての具体的な検討をやっていただいております。これを統一的に六月ぐらいまでには整合性を持たせたいと、それぞれの、根本さんや塩崎さんと私で協議をしておりまして、それぞれのまとめが出た段階で話合いをする予定になっております。
○西田まこと君 この東京が国際金融都市として発展をさせていく、マネーマーケットを国際的に魅力のあるものにしていくという発想は大変に結構だと思いますが、これ過去を振り返ってみますと、こうした言い方っていうんですかね、東京が国際金融都市として発展させるその可能性が高いという主張は、八〇年代後半に中曽根内閣の民活の柱としてまず登場したという経緯があろうと思います。御案内のとおり、四全総とか首都改造計画あるいはそのときのオフショア市場の創設、こうした経緯がございました。
しかしながら、この構想の後、プラザ合意の円高に始まり、地価の上昇、またNTT株の公開による株式投資熱、いわゆるバブルですね、結局、資産の、バブルを招来した経緯というのがございました。
今回の、今大臣の思いを教えていただきましたけれども、この中曽根民活のときの考え方とどう違うのか。また、六月に向けてというお話がございましたけれども、そうしたことを実現していくために予算等、どの程度掛かるものなのか。この辺、もし御説明できるところがあればお話を伺えればと思います。
○国務大臣(山本有二君) 中曽根内閣当時、またその近傍でレーガノミックス、サッチャリズムというような改革もあっただろうというように思いますし、また最近の国際取引におけるグローバル化の進展は著しいものがございます。そういうようなことを踏まえますと、必ずしも中曽根内閣当時の環境とは違う要因がかなりあろうというように思っております。
特に、一九八五年から八九年代、イギリスでは金融サービス部門の経済に与える寄与率は三〇%弱でございました。製造業も同じく三〇%弱でございます。しかしながら、極端に英国病という時代がこれから進展していきまして、もう製造業はほぼ、今も十年前も寄与率はゼロに近いものがございます、経済成長に対して。それに対しまして金融サービス部門のその寄与率は、今やイギリスにおきます寄与率は六〇%になっておりまして、その意味でサッチャーからメージャー、ブレアと来まして、ブレア政権下で二〇〇〇年からのビッグバン、これの新しいシティー、キャナリーワーフという地域に金融拠点を移すことによって新たな段階にこのイギリス経済が入ったと、こういう見方がございます。
その意味で、わずか十年の中からのこの急成長、金融セクターの急成長というものを学習、主にしていきたいとこう考えるところでございまして、これに対して、まあイギリス政府が予算等を使っているというのはまあ言わば環境整備のための予算であろうと思っておりまして、主たるその主人公は民間の金融機関がどういう態度を取られるかということに懸かっておりまして、その意味におきましては、政府としてはやや後ろに下がらなければならないんでありましょうが、今の段階でイニシアチブを取っていただける民間金融機関等についてはございませんので、まあイギリスの例を倣うならば一つのメッセージとして送ることが現在大事であろうという考え方に立っております。
○西田まこと君 まあこの中曽根民活との違い、今お話しいただきましたが、その十年後ぐらいに今度は第二次橋本内閣ではいわゆるビッグバン構想というのが提唱されまして、明確に総理の指示として二〇〇一年には東京市場をニューヨークやロンドンに匹敵する国際金融資本市場にするという指示が当時出されておりました。キーワードは、もう有名になりましたけれども、フリーとかフェアとかグローバルと、こういう大変に正しい方向だったと私も思います。
しかしながら、このビッグバン自体は外為法改正を機にかなり急激に動いたと思いますけれども、当時の金融機関の収益力がまあ余り、正直言って弱かったということを背景にしながら、九七年十一月、まあ七月から始まりましたけれども、金融危機というのが起きまして、その後多額の公的資金を注入する、こういう経緯がずっとあったわけですね。その後再編成が行われて、今メガバンクが利益を計上できるようになってきたと、こういうことでございますけれども。
基本的な、本質的な問題でありますけれども、今回、そういう意味では三度目のこの東京を国際的な金融資本市場として魅力あるものにしていこうという御構想でありますけれども、やはり本質的に日本の金融機関の収益力、あるいは国際競争力というものが本当に充実しているのかどうか、これはメガバンクの十年前の統合前の決算と比べても、まあ資金量は当然増えていますけれども、利益率ということでいうと必ずしも胸を張って言えない状況にもあると。
そういう意味で、外国の金融機関も含めて東京マーケットを魅力ある市場にしていこうというときには、当然競争力のある海外の金融機関が日本に来てそこで切磋琢磨しようということを意味しているんだと思いますけれども、この日本のこういった金融機関の収益力の現状をかんがみて、今回こそ、ある意味でそのグローバリゼーション、今回はそういうグローバリゼーションに本当に堪え得るのかどうか、この辺、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) 橋本内閣当時から起きた現象は、過剰流動性の中で不良債権を生じてしまったというシステムリスクの問題がありました。しかし、あの学習によりまして自己資本比率についての規制あるいは金融機関が学んだ経験からして、土地バブルへの警告判断というような観点から、あのときと同じ轍を踏むことはもはやないだろうというように思っております。
そしてまた、イギリスにおける繁栄は、イギリス自国企業だけでリスクテークをしているというよりも、むしろウィンブルドン現象と言われるように、英国以外の金融機関が英国、特にロンドンのシティーに参加することによっての雇用の拡大や成長の確保ということにつながっているということを考えたときに、我が国も、都市機能的にはもはやロンドンとほぼ互角に戦えるわけでありますし、あとはそのほかの要因がそろえばそうしたことも夢ではないという発想の下に行われるわけでございまして、橋本行革のとき、あるいは橋本総量規制緩和のときからすれば随分環境は変わっているだろうというように認識しておりまして、より具体的に話が進んでいくことができるのじゃないかという期待感を持っております。
○西田まこと君 ということは、国際的な競争を激化させることが、より国内の金融機関の収益力の向上につながる、こういうお考えでよろしいんでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) これは必ずそうなるとも言えませんけれども、民族的な資質、特にリスクテークをしやすい発想の国々と安全第一に考える国々とは、当然やはりそこに企業行動においてもやや異なるところがあろうというように思います。
しかし、やはり同じマーケットの中で、それぞれ同じ立場で収益を競うということになりますれば、これまでのビジネスモデルだけでは済まないという部分がありまして、そこにイノベーションを期待するわけでありまして、特に製造業に比べますと、人材においても、また営業あるいは経営あるいは管理についても、すべて製造業と金融業を比べますと国際化の方は製造業が進んでいると言われておりまして、その意味において新たな段階に日本の金融業界も人材等、能力等、開発が進めば当然伍して戦える段階に来るという期待感は持っておる次第でございます。
○西田まこと君 そういう期待感の裏で、現実に起きている、先ほど来からお話ある日興コーディアル事件とか、あるいは企業と監査法人との癒着というんでしょうか、そういう問題、いわゆる不祥事が続発しておりまして、これはもう言うまでもなくビッグバンの精神にもどう見ても反している事例が続発をしていると。こういう現状ですと、国際金融都市東京というのはなかなか、論じることさえなかなか難しい現実も正直言ってございます。こういうフェアどころかコンプライアンスの徹底そのものが必要というような、非常にある意味では大変寒い現実がございますけれども、これについてはどうお考えでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) これも個々の事象を取り上げればそのようにお感じになるかもしれませんが、やはり全体のマクロで考えていくことによって私は十分可能であろうというように思っておりますし、特に規制におきます物の考え方はここ数年で随分変化があるのではないかと思っております。特に、アメリカにおける規制機関との交流あるいはイギリスにおける規制機関との交流、それぞれ綿密になされている時代になりました。
私も、SECのコックスさんやUKFSAのマッカーシーさんにもお目に掛かれるというように努める、これからしばしば努めていきたいとも思っておりますし、そんなことを考えましたときに、その交流において規制の共通性等々が論じられる時代が来るわけでございまして、日本だけが緩い規制であったり、あるいはきつい規制であったりすることのないような時代が到来するというように期待しておるところでございます。
○西田まこと君 そこで、今日は西室社長にもお越しいただいておりますので、東証さんにお聞きしたいと思いますけれども。
先ほど東証に上場している外国企業の話をさせていただきましたが、外国企業の東証上場が進まないということのみならず、上場を廃止するという外国企業も相次いでいるのも、これ現実だろうと思うんですね。これについて、なぜそうなっているのかということはいろんな議論がありますので、必ずしも証券取引所だけに問題があると言い切れないとは思いますけれども、東証のお立場でこういう現実についてはどんなお考えでしょうか。
○参考人(西室泰三君) 西室でございます。
今の御指摘の問題、具体的に申しますと、東証の外国企業の上場が一番多かったのは一九九一年で、百二十七社を数えました。それが現在二十五社に減っております。非常に急速にこの十数年の間に減ったというのは事実でございます。
それと比較いたしますと、先ほど大臣からもお話ございましたように、ニューヨークにしろ、あるいはロンドンにしろ、非常に大幅に海外上場が増えていると、そういう現実がございます。これは明らかに東京市場が魅力を失ったということであろうかと思います。
東京市場の魅力が何であったか。一九八〇年代後半、特に上場が一番増えたときに、日本の正にバブル経済のピークでございました。日本の経済は、これから先も成長するであろう非常に大きな期待がございましたので、それを期待しての上場というのが残念ながら裏切られたというのが海外の大きな会社の動きでございました。
また一方、東証としての反省を申し上げれば、そのときにどういうふうな形の受入れ方をしたかと申しますと、海外企業の日本への上場ということについて、基本的には個人の株主に対する便宜を図る、逆に言うと、機関投資家の売買を期待しないで日本の国内の個人投資家売買を期待したというふうな形の東証のアレンジがございました。これは、そのときには良かったのかもしれませんけど、その後の世界の中での金融の動きを見ると、明らかに間違っていたというよりは時代に即していなかったということがあったと思います。
そのほかに、無理をしても東証に上場しようという経済環境があった中では、必ずしも手間が掛かる、日本語に翻訳するのが大変だ、いろいろ規制もあって難しいマーケットだというのを、それを無理に無理を重ねて上場されておられたところが抜け落ちてしまったという面もございます。
そういういろんな意味の反省を込めまして、私どもといたしましては、東京マーケットがやはり世界に向かって開かれているマーケットだという情報発信と同時に、内部のいろいろな規制その他の変革も行っております。これから先、反転して、そして海外の上場を増やそうというための手段をいろいろ講じているところでございまして、成果がなかなか出ないのが残念でございますけれども、今年は少しは増えてくると。
二つのターゲットを持っております。
一つはアジア地域、先ほどアジア・ゲートウェイ構想、その他いろいろ話題に出ましたけれども、アジア地域の企業の上場を何とかインバイトしたい。特にアジア企業の成長を担う、エマージングマーケットと申しますが、成長していくアジア企業の上場ということで、昨年の十一月にマザーズにマザーズ・グローバルというのをつくりました。これは、なぜマザーズ・グローバルをつくったかといいますと、それぞれ外国企業が上場される、しかも小さい成長していく企業でございますから、リスクが日本の企業と違ったものがございます、それぞれの国のリスクもございます。それが最初からちゃんと分かるように、つまりリスクマネーを供給していただくという個人投資家、そういう方々に最初からこれは外国の企業が上場しているんだねというのを御理解いただいて投資をしていただく、そのためには少し規則も変えてございます。そういうことを一つ手を打って、更にアジアを中心にして上場企業を増やそう。
もう一つは、実は欧米のブルーチップ銘柄、これがその抜け落ちた約百社のほとんどでございますので、これをもう一度帰ってくるように頑張りたいということで、新聞などで報じられているようなブルーチップ銘柄も日本に戻ろうかと。
つまり、日本に上場することが意味があるんだと、意味が二つあるだろうと思います。
一つは、日本の個人金融資産一千五百兆円、それを始めとして、今朝ほど大臣からもお話がございましたように、株式市場に向かっている個人金融資産が少な過ぎる、それがトレンドが変わってくればはるかに大きな資金供給が期待できるというマーケットにしていくということが一つございますし、それからもう一つは、やはり日本の市場そのものの中でプレゼンスを確保することが外国企業にとって有利であるという状況、つまり日本の経済そのものがこれから成長していくんだから、その一翼を担うというふうな形での進出というものを期待したい、そういうふうに考えていろいろとやっております。
以上でございます。
○西田まこと君 そういう中で、一方、東証としては上場問題を抱えながら、同時に主要国の証券取引所との提携についても進めようとなさっておられると思います。今の魅力ある市場にしていくというところでの様々な施策の中にも、こうした東証自体のグローバリゼーションということもあろうかと思いますが、この点についてはどんなお考えでしょうか。
○参考人(西室泰三君) グローバルに開かれていく市場を形成するために私どもとしてはやらなければならないことがたくさんございますけれども、具体的に申し上げて三つ大きく取り上げて見さしていただきたいと思っております。
まず一つは、東証そのものの市場の信頼性を確保するために東証の自主規制機能というものを更にはっきりと独立性が確保できるように、しかも内容が優れている、そういう自主規制機関であるということを内外に分かるように示す必要があるというふうに思っております。それを一つの重要な目的として、今年の六月に株主総会で方向付けを決めさせていただいて、金融取引法、多分七月に施行していただけると思いますので、それが施行された後で十月一日を期して持ち株会社方式に変えさしていただき、持ち株会社の下に今度の金融商品取引法で許されました自主規制法人というのを独立の形でグループの中に持つという形にしようというのが一つの方策でございます。
それから二つ目は、システムそのものの増強と近代化というよりは、世界最先端の取引システムをなるべく早く導入していくということだと思います。
香港から始まった世界の同時株安が世界を一巡りしました。その過程の中で、東証は幸いに安全でございましたけれども、ニューヨークも、そしてロンドンがございましたし、それからその他幾つかの市場で市場の一時閉鎖あるいは機能低下、そういうものが見られました。その中で東証は何とかつなぐことはできましたけれども、ただ、東証が持っている現在のシステムというのは世界的には遅れています。それを全面的に入れ替えるという作業を次世代システムの構築という名目でやらせていただいております。約三百億ぐらいの投資を三年間でやって、二〇〇九年に世界最高水準のものを築き上げようと。これが二つ目でございます。
それから三つ目に、我々が考えておりますのは、そういうふうなバックグラウンドで世界に比肩できるような仕組みをつくって、それができる前から世界のほかの取引所との提携を深めて我々の上場商品を更に拡大し、そして商品の広さと厚さについても東証は魅力的だと、国内の投資家の方だけではなくて、海外の投資家の方にも思っていただくと、そういうことをやっていくということが三つ目でございます。
よろしくお願いいたします。
○西田まこと君 そうした東証自体の体制の改革とか、様々なグローバリゼーションということがどんどん進んでいくという一方で、今大臣からお話がありましたとおり、東京の国際金融マーケットとしての魅力を高めていくという。東京に金融面においてもかなり、そういう意味ではかなり魅力のあるインフラが育っていくということによりなっていくんだと思うんですね、加速度的に進んでいくと。
そうすると、日本国内にある証券取引所はどうするのかと、その再編成の問題というのも一方にあろうかと思うんです。金融面での東京、ちょっと言えば一極集中みたいなことと、一方では各都市に証券取引所があった方がいいんじゃないかという大臣のお考えもちょっとメディアに出ていたようでありますけれども、こうした東京のマーケットを国際的に魅力のある市場にしていくということがどんどん進んでいくという一方で、それぞれの地域のこの証券取引所をどういうふうにしていくのか。国内の証券取引所の再編成の問題につきまして、現状でのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) 量においても質においても圧倒的な存在でございます東京証券取引所、それを中心にしまして業務の提携やあるいは共通化によって、それぞれの地域の証券取引所も独自の地域経済を担う主要機関としての証券取引所の存在としては尊重しながらも、そこに関連をしていくということは大事なことだろうというように思っております。
特に、福岡の証券取引所における自主規制機関における事務方は一人か二人しかいないという現実を考えてみましても、当然そこにおける審査判断についての自主規制提携は東証とやっていっていただかなければ具体的には難しいという面もあろうと思っております。
そうしたことを考えながらも、例えば御党から提案がございましたアジア・ゲートウェイにおける拠点を関西にというような提案は、それはそれでかなり具体的ないい御提案でないかというようにも思っております。今、アジア・ゲートウェイ担当の根本さんのところでもそのことを踏まえながら研究に入っているというように聞いておりますし、これから東京だけが経済的中心ではないという意味において、それぞれの地域がそれぞれの特色を生かしながらの金融機能の拠点となり得るという日本になれば、なおよろしいんじゃないかというように思っております。
○西田まこと君 ありがとうございました。
最後に、五分ですけれども、西室社長はこれで結構でございます。ありがとうございました。
中小企業向けの動産担保融資についてちょっとお聞きしたいと思いますが、この担保という概念がこれまでとはやっぱりだんだん変わりつつあると。あえてざくっと申し上げれば、債権者のための担保から債務者のための担保、つまり会社がもう本当に厳しくなったときに最後、担保でどうするかという話ではなくて、在庫にしましてもそれを使って中小企業が資金調達をしていくという積極的な意味での担保、債務者が活用できる担保、こういう考え方というのに少しずつツールも含めて変わってきているんだろうと思うんです。
そこで、中小企業向けのこの動産担保融資について、いわゆるリレーショナルバンキング、リレバンの中において、金融当局としてもどういうふうに位置付けておられるのか、これをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(佐藤隆文君) 御指摘いただきましたように、中小企業向けの資金供給の円滑化と、こういう観点から動産担保の活用といったようなことを含めまして、融資手法の多様化を図るということが重要であるというふうに認識をいたしております。
この動産担保融資につきましては、中小企業等の多くが動産、言わば在庫等を中心としたものを有しているという状況でございますけれども、これまでは必ずしも十分に活用されてこなかったということでございます。したがいまして、動産担保融資の推進というのは、中小企業の言わば資金調達手段を従来以上に多様化するという効果があるものというふうに認識をいたしております。
金融庁は、御案内のとおり、平成十五年度から地域金融機関に対して地域密着型金融、リレーションシップバンキングの機能強化というのを推進しておりますが、その中で動産担保融資の推進など、不動産担保あるいは個人保証に過度に依存しない融資手法というものを推進しているわけでございます。
現実に最近の事例といたしましては、在庫を活用した、動産担保として活用した融資手法が広がりつつあるということでございます。例えば、海産物の卸売業が昆布等の在庫を活用した事例とか、あるいはフカひれの加工業者が在庫であるフカヒレを活用してABLを実行したと、こんなケースが出てきているところでございます。
今後とも、金融庁といたしましては、動産担保の活用など、不動産担保、個人保証に過度に依存しない融資手法というものの推進、多様化に努めてまいりたいと思っております。
○西田まこと君 是非そこはどんどん進めていただきたいと思いますが、この動産担保融資を本当に普及していこうと思うと、やはり金融庁による適格担保の認定ということが大変重要な要素になってくるんじゃないかというふうに思うんですね。
新BIS規制の実施に伴う告示がございますけれども、そこで適格その他資産担保の中には船舶、ゴルフ会員権、航空券のみが列記されていると認識しておりますけれども、特に中小企業向けということでの動産担保融資をもっと広めていくために、もうちょっとこうした限定列挙のところをもっと広げていく必要もあるんじゃないかと、こう思いますけれども、いかがでございますか。これを最後の質問にさせていただきたいと思いますが。
○政府参考人(佐藤隆文君) 御指摘の点につきましては、今手続を進めておるところでございますが、広げる方向でその作業をしているということでございます。
○西田まこと君 終わります。
○委員長(家西悟君) 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
○西田まこと君 公明党の西田まことでございます。
今回のこの国税二法につきまして、尾身大臣にお聞きしたいと思います。
まず、この小泉政権における財政改革ということと、この安倍政権における財政改革ということでは、当然時期も異なることもあるんですけれども、課せられたこの改革の課題というのが当然違ってくるんだろうというふうに思っております。
私自身のまとめ方で申し上げますと、小泉財政改革というのは二つの条件、すなわち新規国債発行枠を三十兆以下にするということ、また消費税は上げないということで、不況下における緊縮財政を徹底をするということによる財政改革がテーマであったと思います。そこにおきまして、とりわけ民間企業が、いわゆる三つの過剰と言われる過剰雇用、過剰債務、過剰投資、こうしたことから、この三つの過剰ということで三Kと仮に申し上げますと、この三Kからの脱却ということを民間企業が行ってまいりまして、経済が復活してきたんだろうと、こういうふうに思うわけでございます。
最初に尾身大臣にお聞きしたいのは、この安倍政権におきまして、この財政改革の課題は小泉改革とはどこがどう違ってくるのかという御認識をまずお聞きしたいと思います。
○国務大臣(尾身幸次君) 安倍内閣におきまして、成長なくして財政再建なしという大きな考え方がございます。つまり、経済の成長を実現しつつ財政再建を進めていきたい、つまり財政再建と経済成長は矛盾するものではなくて補完をするものであるという考え方でございまして、この経済の活性化をしっかり実現をする、同時に財政再建も実現をすると、こういうことでございます。
今、委員のおっしゃいました国債発行額、小泉政権の課題といいますか実現したこと、国債発行額を三十兆円以下にする、そして消費税を上げないと、こういう二点に集中してきた。おっしゃるとおりのこともよく理解はできるわけでございますが、しかし、今年、十九年度のじゃ財政がどういうことかといいますと、この財政の規模が一般会計で八十三兆円であります。
この収入の内訳を見ると、税収が五十七・五兆円、公債が二十五・四兆円で三十兆円を切った公債発行でございますが、なお全体の財政規模の三〇%を超えているというような状況でございまして、しかもいわゆるプライマリーバランスもまだまだ国、地方を合わせて赤字であると、こういう実態になっておりまして、まだGDPに対する債務残高が雪だるま的に増えるような構造になっているということは否めない事実でございまして、私どもは、この点をプライマリーバランスの黒字化とともに達成をしていくためにこれからも全力を尽くしたいと思っております。
○西田まこと君 正にこの雪だるまをいかに小さくしていくのかという先ほどお話もございました。
そこの国債残高の膨脹ということについてどう考えるかをお聞きしたいと思いますが、今回、この特例公債法の第二条四項のところを見てまいりますと、特例公債につきましては速やかな減債に努めるというふうになっているわけでございます。しかしながら、現状を見ますと、平成十七年度の時点で建設公債とこの特例公債の残高は既に逆転をしておりまして、特例公債の方がもう建設公債よりも残高としては増えていると、こういう現状でございます。
なぜこうなっているかといえば、特例公債におきましては一九八五年に差し当たりの政策として六十年償還ルールというものを適用しているわけでございますが、差し当たりの政策と言いながらもずっと差し当たりが続いてきておりまして、その結果、この特例公債の残高というものが建設公債よりも上回ってしまっていると。
そうしますと、今回この特例公債の第二条第四項にあるような速やかな減債に努めるというのは、これは特別だよということで特にこの記載がなされてきているわけにもかかわらず、こうした特例公債残高が増えてしまっている。過去、平成六年だったでしょうか、記憶が正しければ、六十年償還ルールではなくて、二十年償還ルールというふうに特別減税の際にやっていたということも承知しておりますけれども、基本はずっと六十年償還ルールで、特例公債の残高がどんどん増えてしまっている。
この法律にあるような速やかな減債に努めるという記述と、現状がむしろ建設公債よりも特例公債の残高が増えてしまっているという、この辺についてどうお考えになりますでしょうか。
○国務大臣(尾身幸次君) 財政法では、建設公債は発行が認められているわけでございます。例えば道路とか港湾とか空港とか、後世代がそれを活用するものであるという意味において認められているわけでございますが、特例公債についてはその都度国会の議決を経て御了承をいただくと、こういうことになっておりまして、通常、これは原則的には認められないものでございます。
その特例公債の残高の方がいわゆる建設公債よりも多くなってきているということは、財政の状況が非常にアブノーマルであるというようなことであると私どもは自戒をしておりまして、二〇一一年度に、先ほど来のお話のとおり、国、地方のプライマリーバランスを確実に黒字化させることを目標にしているわけでございまして、同時に、プライマリーバランスそのものが黒字化したとしても、利払いを含みます財政収支は依然として大幅な赤字が続き、国と地方を合わせた長期債務残高も極めて高い水準にあるということでございまして、これを何としても少なくしていかなきゃいけない。
そういう中で、日本経済の進路と戦略におきまして、二〇一〇年代半ばに向けて国、地方を通じた収支改善努力を継続して一定のプライマリーバランスの黒字幅を確保して、債務残高GDP比の発散を止め、安定的に引き下げることを確保することを目指していきたいというふうに考えている次第でございます。
○西田まこと君 正にこの、先ほど中川委員からも御指摘ございましたけれども、プライマリーバランスの均衡あるいは黒字化といっても、これは一里塚にすぎないわけでございます。
お手元にお配りさせていただきました三枚目の方ですけれども、国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算というのが財務省から出されております。これを見ても一目瞭然でございますが、国家の財政においてプライマリーバランスの均衡というのは、家計に例えれば、生活費は収入で賄うけれども、住宅ローンなどの借金の元利返済は新たに借入れを起こして返済していくということになっているわけでございまして、これが健全でないことはだれが見ても明らかなわけでございます。
所信のときにも御説明いただきましたが、新規国債発行額は過去最大の減額になっていることは事実でございます。しかしながら、お手元のこの仮定計算見ていただくと分かるように、この新規国債発行額が二十五兆になった一方で、その後ろには百十三兆円もの国債が満期を迎え、要償還額としてなっております。このうち、償還財源があるもの、現金償還というのはいろいろ足すと十一兆円ぐらいしかないわけでございまして、借換えによる償還が九十九兆八千億円にもなっていると。つまり、ネットで見ますと、十一兆円しか現金で返さないのに新規二十五兆円借りていると、こういうことになるわけでございますので、国債残高は十四兆円分ぐらい増えていくと、こういう構造になっていくんだろうというふうに思います。
この償還財源は六十分の十しか積み立てられていかないわけでございますので、今後新規国債発行額が極端に言えば十兆円以下にならなければ、これは国債残高は減らないということに単純に考えればなるわけですけれども、これだけ大幅な歳出カットとかなかなか難しいというのもまたよく理解もできるわけでございます。
そこで、先ほど大臣がおっしゃったように、成長なくして財政再建なしと、こういう成長促進型の財政再建ということになるんだろうと思います。私もそれはそうだろうというふうに、正しいんだろうというふうに思うわけでございます。
そこで、この成長、じゃどんな成長によって財政再建をしていくのかということが次に焦点になってくるんだろうと思います。
昨年、政府税制調査会におきまして、今後の検討課題の一つとして法人実効税率の引下げの問題が提起されたというふうになっておりまして、ここで法人税率の一律引下げに関してのお話をさせていただければと思います。
この法人税率の実効税率どうするか、これから決めるということはもうよく重々承知した上で、一つの議論として是非大臣の方からいろいろと教えていただければと思っておりますけれども、法人の実効税率が四〇%を仮に三〇%に下げた場合には、これは決して一〇%法人税率を下げたということではなくて、当然二五%下げているわけですね、四〇から三〇ですから。その上で、仮に四〇から三〇に下げたときに、同じ法人税収を上げていくにはどうしたらいいのか。これは、単純な算数で計算しますと、企業の収益が三三%増えなきゃならないわけですね。ですから、法人実効税率を下げたときに、法人税収が全国おしなべて、平均して三三%増益と、そのぐらい成長を促すと、法人実効税率が、四〇から三〇に実効税率を下げたときに、というふうにならなければ税収が不足するというか足りなくなるということになるわけなんです。
しかし、三三%の増益というのはかなり高い。法人実効税率を四〇から三〇に下げただけでそんなに効果があるものなのかというには、私はやや魔法に近いものがあるんじゃないかというふうに単純にいえば思うわけでございます。
また、企業減税が成長率をどの程度押し上げるかというのは、これまた多分世界一優秀なエコノミストでもなかなか正確には予想できないんだろうというふうに思っておりまして、今後の検討課題の一つとしてという前提でございますのでお答えにくいのかもしれませんが、この法人実効税率を引き下げるという場合のコスト・ベネフィット分析ということについて大臣どうお考えか、教えていただきたいと思います。
○国務大臣(尾身幸次君) この法人実効税率につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、企業が国を選ぶ時代になりました。ですから、日本の企業といえども、また外国の企業といえども、どこに生産活動の拠点、事業活動の拠点を置くかということは自分で決める。つまり、日本の大企業といえども、これから設備投資をしたり事業活動の拠点を置くときに日本を選ぶかどうかは分からない。中国とかあるいはインドとか、あるいはほかの国々を選ぶかもしれない。そういう中で、つまり企業が国を選ぶ時代になった中で、日本という国が企業活動の拠点として選ばれるような魅力ある国にならなければならないというふうに考えております。
そのためには、税率の問題、それから技術の問題、人材の問題などなどいろんな要因を考えるわけでありますけれども、少なくともこの税制については、イコールフッティングの、ほかの国とイコールフッティングの税制を構築する必要がある。つまり、税制面で少なくとも条件が日本だけ悪いというようなことは避けなければならない。
そういう意味で、減価償却の償却率を一〇〇%にするという改正を今度するわけでありますが、実効税率で見ますと、日本は大体四一%、アメリカと並んで世界一高い。ドイツが今約四〇%で同じ水準なんでありますが、ドイツは最近これを三〇%に下げるというような話も聞いているわけでございまして、あと、アメリカ三五%、フランス三三%、イギリス三〇%、中国三三%、韓国二七%というような水準になっているわけでございまして、世界全体のいわゆる企業誘致競争の中で、世界的な傾向としてその法人税率を下げるという傾向にございます。
さはさりながら、そういう先ほど述べた要請はございますけれども、それじゃ簡単に日本の法人税率を下げられるかというと、これは今の財政厳しい状況の中でそう簡単にいかないという、言えば背に腹は代えられないという事情もございまして、ここで四〇%を、四一%を三〇%に下げたらどういう経済効果があるかというようなことを申し上げると、尾身財務大臣は下げるつもりになっているんじゃないかというようなことを誤解を招きかねないわけでございますし、したがいまして、四〇%を三〇%に下げればどのくらい企業活動が活発化して、税収がその面から増えるか。他方、四分の三になるわけでありますから、それが減る、そこをどうするかというような問題を総合的、立体的に考えて、先ほどの企業が国を選ぶ時代になったということを踏まえながら考えていかなければならない問題であろうと考えておりまして、なかなかその辺をどう考えていくかは今後私どももしっかり勉強させていただきたいと思うところでございます。
○西田まこと君 正に企業が国を選ぶ時代になってきているということはもうそのとおりだろうというふうに思っておりまして、そういう中で、今私が一つの議論として大臣から教えを請うたのは、正にこの法人税率を引き下げたことで税収がその限りで企業増益になって穴埋めができるかどうか、これはやってみなきゃ分からない、それはそのとおりだと思うんです。
ただ、議論として申し上げれば、これ、法人企業のうち税金を納めているのは全体の三割ということになりますし、法人税率を一律引き下げて、その分法人税だけで増益による税収増というのもなかなか難しいんじゃないかと、こう考えると、負担する候補はだれかと。こういうふうに考えますと、もうこれは明らかに個人所得税か消費税しかないというふうに大体なるわけですね。ほかにも細かいこといろいろありますけれども、大きく言えばそういうことになる。
しかし、じゃ、その個人が、あるいは家計がそういうことを負担できるのかどうかということで、お手元にこの表一から表六までの表を作らせていただきました。
これは日本とドイツとアメリカをそれぞれの各国統計から抜粋をいたしまして作成したものでございまして、ベースは名目になっております。なぜ名目か、普通はこの手のものは実質でやるということは承知しておりますけれども、日本のデフレということをより鮮明化し、また独、米においてもディスインフレになっているということも勘案して、名目GDPで記載をさせていただいております。
表一を見ていただきますと、日本の個人消費の内訳、また全体の名目GDPもございますが、この二〇〇六年、一番下の名目GDPが五百七兆ですけれども、十年前の九七年、五百十五兆円をまだ下回っているという状況であります。それに伴いまして、家計最終消費支出を見ても、ようやく二〇〇六年、若干上向いていますけれども、十年前とそんなに変わらない水準であるということ。所得の伸びがゼロということに対応して消費の伸びも大したことないと、こういう対応がすぐ見て取れるわけであります。
一方、一番右側に参考として国民総所得というのがございますが、これは海外からの所得受取超過ということも含めた所得になります。この九七年のところを見ていただきますと、名目GDPとの差額が、今申し上げました所得の受取超過になりますが、これが大体七兆円。二〇〇六年にはこれが十五兆円になっていると。これは何を意味しているかというと、企業とか資産運用のグローバリゼーションということによって、海外からの所得受取超過が倍増していると、七兆円から十五兆円になっていると、こういうことであります。これは国内の生産には必ずしも直結していないと。分かりやすく言えば、今日本の大手企業の連結で見た場合の営業利益は、年々比率は高まっていますけれども、三割は海外で上げているわけであります。その海外で上げている利益につきましては、じゃ国内の雇用がそのまま増えるのかというと、直接的にはなかなか増えない。その部分が今国民総所得と名目GDPとの差額として大変に増えてきているということが見て取れると思います。
次のドイツの個人消費。ドイツをなぜ挙げているのかといえば、これはこの一月から消費税率が三%引上げになりました。一方で、法人税率を、先ほど大臣もおっしゃっているように、引き下げているという背景がございましたので、あえて比較をしているだけでありますけれども、これを日本と比べてみてすぐ見て取れることは、日本とは異なって、ドイツの場合には名目GDPは増えている、そして消費も増えていると、こういうことが見て取れます。
ちょっと時間の都合でアメリカは省かせていただきますが、二枚目の表四を見ていただきますと、しからば、この日本とドイツの労働分配率がどうなっているのかということを、要素価格による国民所得を分解する形で示させていただいております。
この一国の付加価値がどう分配されているかというのをそこで見ているわけでございますけれども、一番左側の日本の国民所得は、雇用者報酬と財産所得、企業所得というふうに分けられるわけでございますけれども、この雇用者報酬を見ていただきますと、二〇〇六年、二百六十兆になっておりますけれども、この九四年、一九九四年とほぼ同じというか、そこにほぼ横並びですね。雇用者報酬はそういう数値になっております。労働分配率はそういう意味で下がってきて、今いろいろと話題になっておりますけれども。ドイツの方も労働分配率は同じように下がってきている。大体ドイツの、右側ですけれども、ドイツの被雇用者所得と財産所得、企業所得というのを見比べてまいりますと、被雇用者所得は国民所得増加分の二割強しか増えていないという、八割が企業所得。こういうことがありまして、今メルケル政権の下で労働分配率も上げていこうというようなことが大変に動きとしてあると承知をしているところでございます。
その下の表五、日本の所得分配状況・内訳を見ますと、雇用者報酬の内訳、賃金・俸給ですけれども、これを見ていただきますと、二〇〇二年ぐらいから二百二十兆円前後にずうっと賃金・俸給は停滞していると。九七年のときには二百四十兆円もあったわけですけれども、今回、二〇〇五年では二百二十兆。
で、右側の雇主の社会負担を逆に見ていただきますと、マクロで見ると意外と社会負担増えてないということが分かるかもしれません。
その更に右側の財産所得を見ますと、これはかなり衝撃的になっておりまして、十八兆ありました、家計純利子は九四年には十八兆ありましたけれども、まあ、低金利というのは今最近に始まったことではなくてずっと前からどんどん低金利になっていたわけですけれども、その影響もありまして、二〇〇三年、二〇〇四年、二〇〇五年と、それぞれもう支払超過に家計純利子はなっていると、三兆円ですね。ですから、家計の純利子の所得というのは、九四年から比べますと二十二兆円消滅をしているということになります。
一方で、その隣の家計受取配当というのが二兆円から六兆円に増えている。つまり、いわゆる貯蓄から投資へという流れもあるんだと思いますけれども、家計受取配当はプラス四兆円と。ただ、ネットで見ますと、二十二兆円消滅して四兆円増えているという、十八兆円減っていると、こういうような様子が見て取れるわけでございます。
今、長々とちょっと説明させていただきましたけれども、マクロ全体で見たときに、法人税率を引き下げる、それをだれがじゃ負担をするのか、企業だけでできるのか。なかなか、魔法のような、三三%増益の企業がそんなに一杯急に出てくるのかと。これはなかなか多分難しいだろうと。実際三割の企業しか法人税は負担していない。となれば、家計がそれを穴埋めすることにマクロとしてはなるんではないかと思われます。
しかし、それに堪え得るような今家計の状況なのかと見ますと、今、私が長々とちょっと説明させていただきましたけれども、なかなかその負担をできるような状況には今ないんではないかというふうに私は率直に思うわけでございまして、今ちょっとるる説明させていただきましたけれども、こうしたことを背景にして、先ほどと同じ質問になりますけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(尾身幸次君) 法人税率、ドイツは四〇%の法人税率を三〇%まで下げる、他方、消費税一六%を一九%まで上げると。これをセットといいますか、やるというようなことを聞いております。
で、ドイツの場合には、私も詳しくは存じませんけれども、EUに東ヨーロッパの国が入ってきた。安い賃金の労働力があり、かつ、いわゆる技術水準やなどもほぼそんなに違わない。そういう意味で、法人税率を下げないと企業が外国に行ってしまうということで、法人税率を下げて消費税率を上げる、そしてそれによって企業を国内に残して、生産活動の拠点としてドイツ本体を残していくというような考え方で、そういう税制改正を国民の皆様が理解をしているのではないかと推測するわけでございます。
日本の場合には、私はかねがね、企業が国を選ぶ時代になったというふうにいろんなところで申し上げておりますが、そのいわゆるホローイングアウトというか、企業の国外流出というのが一時と比べますと少し止まっている。つまり、国内である程度基本的技術を温存していないと世界的な競争ができないという配慮も私はあるかと思っておりますが、そういう中で、企業が国を選ぶ時代になったということの認識といいますか、そういうものがまだそう深刻ではないために、ドイツと違ってなかなか国家的なコンセンサスが得られないという状況であります。
しかし、全体としてはドイツのような状況には、グローバリゼーションの中で、世界経済、グローバリゼーションの中で、そういうことを考えていかなければいけないのかなと。しかし、他方で、財源の問題もありますし、国民の皆様の